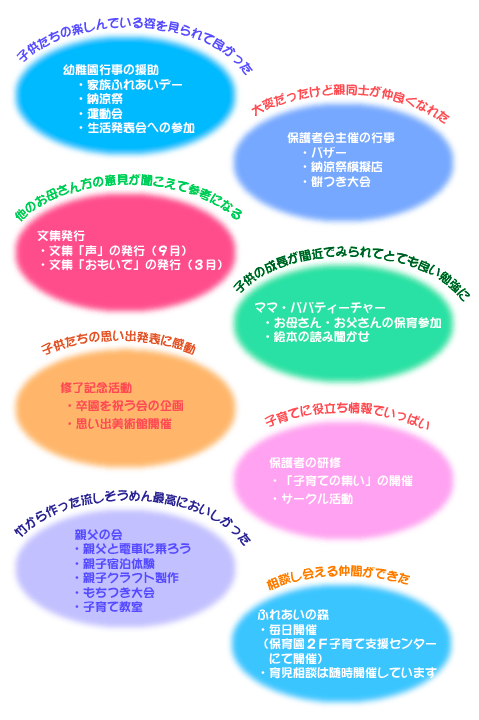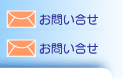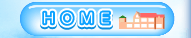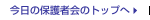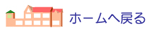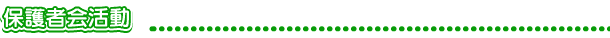


群馬で生まれ育った方なら、誰しもやったことがあるでしょう。県外の人に聞くと、郷土を題材にしたカルタがこれだけ広まっているのは、珍しいそうです。群馬を少し知っている人に群馬のイメージを聞くと、「焼きまんじゅう、とりめし、上毛かるた」と言われることが多いです。
私もよく小学校の頃やりました。「和算の大家 関孝和」をよく「親戚?」と何度も聞かれ、嫌になった思い出もあります。そして、男子は「世のちりあらう四万温泉」をとると・・・・・。
そんな上毛かるたのそれぞれの札をわかりやすく書いた、「「上毛かるた」で見つける群馬のすがた」という本が、群馬県から発行されています。小学校4年生の副読本としても使われているそうです。就学前の子供さんですと、”かるた”そのものが難しいと思いますが、我が家では「雷と空っ風・・・」の絵札を見せて、「怖いねえ」とか言ってます。本もかるたの懐かし感があって、大人でも十分楽しめますので、興味ある方は大きめな書店をのぞいてみてはいかがでしょうか?
話は変わりますが、「力合わせる○○万」の○○の数をお近くの人に聞いてみてください。その方のだいたいの年代が分かります。
今は200万ですが、この数字は国勢調査の人口で決まります。一時期、200万人を割ったなんて、話もありましたが、最近の新聞で辛うじて200万人を維持と知りました。
「かるたを作っている会社、よかったですね」なんて。
保護者会長 關(「銘仙おりだす伊勢崎市」出身)

昨日(1/25)の数社の新聞に大きく取り上げられていました。
「認定こども園て何ですか?」
「い〜い質問ですねえ。こども園というのは、幼稚園と保育園の機能を併せもってですね・・・・」と池上彰さんなら説明できるのしょうけど、私十分な理解も、上手な説明もできません。すみません。でも、少し関心を持っていく必要はありそうです。
保護者会長 關

松居先生は東京都杉並区に住んでいらっしゃいます。自宅の建物は、篠原一男さんという業界では有名な方の設計で、「白の家」という名前でいろいろな建築雑誌に取り上げられています。その名のとおり、外壁は白の漆喰で塗られており、決して広くはないのですが、いい感じの古民家風の住宅です。知る人ぞ知る今は無き、名番組「渡辺篤史の建物探訪」にも出たそうです。
私はいろいろな建築住宅を見るのが好きなので、松居先生の住宅を知っていたのですが、この話題を出したとき、先生が「何で知っているのですか」と大変驚かれたのが、印象に残っています。
設計した篠原氏の考えに感銘したこと、また、道路拡張のため、一度取り壊し、再度同じ材料で立て直したこと、海外からも見学者がやってくることなどを話していただきました。
興味ある方、インターネットで「白の家 篠原一男」で検索するとすぐヒットすると思いますので、ご覧あれ。
保護者会長 關

松居先生の講演会後、園と本部役員とで先生と懇談する機会がありました。先生には、息子さんが2人、お嬢さんが1人いるそうです、長男は10年前にも園に講演にきた、友(とも)氏。フィリピンミンダナオで貧しい子どもたちへの支援活動をされています。二男は、和(かず)氏。現在、埼玉県教育委員会教育委員長をされています。長女は、さち(漢字不明)さん。絵本作家で、ペンネーム=小風さちで活動されているそうです。ちなみにペンネームは、松居先生がつけられたそうで、「宝塚みたいでいいでしょ」と笑いながら、言っていました。
こんな話もありました。先生が息子さんから「海外に行って勉強したい」と相談を受けたそうです。そのとき、先生は、先進国でなく、発展途上国へ渡ることを勧め、帰りの切符も一緒に飛行機のチケットを買い与えたそうです。ところが、息子氏はそのチケットを売り払い、アメリカへ留学されたそうです。その方は、自動車でユーラシア大陸を横断する経験もされたとか。先生の穏やかな性格から、想像もできない、豪快な息子氏だと思いました。
そんな先生の話を聞きながら、感じたことは、「生きる力をつけることの大切さ、命の大切さ」です。例えば、無人島につき、食料もなく、ガス・電気もなく、怪我や病気になったら・・・
私には答えが分かりません。分かろうとして、発展途上国に行こうとも思いません。子育てと仕事で精一杯です。
でも、今のように物に満ちあふれた時代にいなかった先人たちは、命の尊さを(頭でなく)心で感じ取り、その答えを一つづつ見つけていったのでしょう。そして、その答えが見つかったとき、喜びを皆で分かちあったのでしょう。
食べられる木の実を発見したときや落ち葉でたき火をしているとき等自然に触れているとき、何かを発見したときの子どもの表情は本当に活き活きとしています。先人たちの喜びの笑顔(嘘のない本物の笑顔)と同じなのだと思います。
雪遊び、キャンプ・・・たくさん経験させてあげたい!でも、お金がないから、山上城址公園で、落ち葉、木の実拾い!!なんて思った、懇談会でした。
保護者会長 關(城址公園でお尻に段ボールを敷いて坂を滑り降りる遊び、おすすめです)

松居先生のお話では
物やお金に執着すると、「命・言葉・心」がおろそかになってしまう。
絵本は読むのも勝手、聞くのも勝手
絵本の絵は見るのではなく、読む物
人に言われて頭にいるのではなく、
「自分で感じて心に残す」
のちに 命・言葉・心 がみえてくるのではないか・・
私は先生の話の一つ、
子供が言葉を覚える過程で、
家庭内の会話が与える影響力の大きさ。
はっとしました。
そういえば大人が話す会話に口を出して良くしかられました。言葉使いを気をつけ、もっと綺麗な日本語を使いたいと思います。
皆さんはどう感じましたか?
今回の講演が皆さんの心に残りましたでしょうか?
田中
![]()